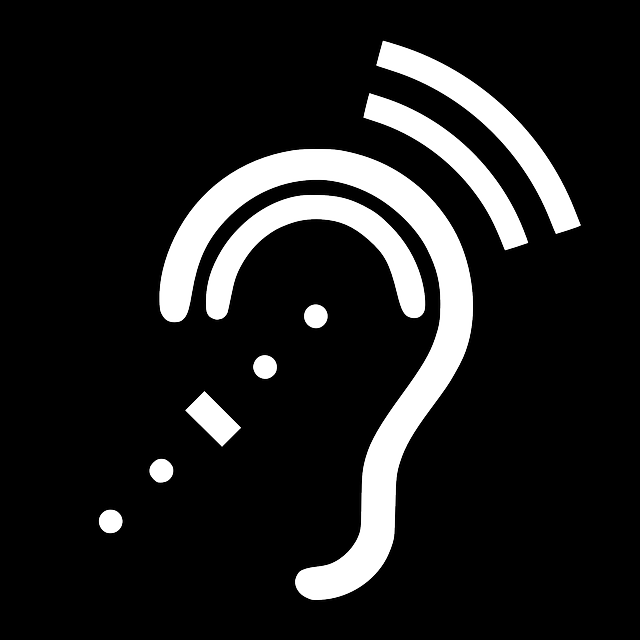こんばんわ。親からまたしてもりっぱな白菜を送ってもらいました。あおが帰ってくる前に白菜の浅漬けを作っていたのですが、うますぎて食い過ぎたら胃がいたいくらげです。
補聴器にある謎の機能
昨日のブログは聴覚障害者でも音楽を楽しむ人がいて、一人一人聞こえ方が違うという内容でした。
本日はボクが音楽を聴いている補聴用オーディオ器具の紹介です。

こんなんです。ネックループとMリンクプラスです。いや、紹介されても「なんだこれ」となる人が大半でしょうけど。
補聴器や人工内耳には誘導コイルという装置がついているものがあります。
原理的には非常に単純で、電気が流れるときに発する磁気を補聴器で受信して音に変換するもの。
磁気を発生するループを教室や会議室に張り巡らせ、補聴器に直接音を届けることが出来る仕組みなんですね。
これだと話す人やスピーカーから距離があっても音が小さくなりません。
ただ、磁気なので混線はひどいです。電車の中ではモーターの磁気で雑音がひどく使えません。
今ではFMシステムやBluetooth搭載の補聴器も登場しており、これらを使うと非常にクリアに聞こえますが、誘導コイルは安価なので未だに主流です。
ボクが誘導コイルを使う理由
で、ボクの補聴器・人工内耳にも誘導コイルがついています。
写真の機器のループ・フックの部分にはコイルが入っており、イヤホンジャックに差すと音楽にあわせて磁気が発生して音楽を補聴器・人工内耳で楽しめるわけですね。
誘導コイルで音楽を聴くと、イヤホンだとぼやけた音もそこそこシャキッと聞こえますが、その反面、低音域がすかすかになってリズムが取りにくい。
そこで、片耳が普通のイヤホン・もう片方が磁気ループのMリンクの出番です。
ボクの聴力だと、標準的なオーディオ機器を最大音量にすると、低音域部分はなんとか生音で聞き取れます。
高音域や歌詞は誘導コイルを通じて人工内耳、リズムはイヤホンと役割を分担させて音楽を聴いているんです。
どんな聞こえ方なのか
この感覚はかなり説明しにくいのですが、絵に例えるなら、人工内耳から拾う音はハッチングのようにはっきりしていますが、色彩が乏しい。
逆に生音は輪郭がぼやけて形をとらえることが出来ませんが色は生々しく表現されています。子どもが描くクレヨンの絵みたいなもんですね。
この二つが組み合わさることで、音楽としてはそこそこ形になっているなぁと感じています。
以前はイヤホンだけで聴いていたのですが、このスタイルを知ったときは本当に世界が変わりましたねぇ。
一方、講演会やイベントでは両耳がはっきり聞こえた方がいいので、両耳に磁気をとばせるネックタイプの強力なループを持っていきます。こちらは音がよく音量も大きめですね。
補聴器の機能の説明をしていきます
聴覚障害というと「補聴器」については知っている人も増えていますが、こういう補聴器のアクセサリーや機能を詳しく知っている人は多くない。
しかし、機能を使いこなすことで聴覚障害があっても豊かな音の世界を楽しめることがある。
というわけで、これから少しずつ、補聴器の機能やアクセサリーを紹介していたいですね。
「補聴器についてこういうことがしりたい」という要望がありましたら、メールフォーム等からご連絡ください。
では、おやすみなさいませ。