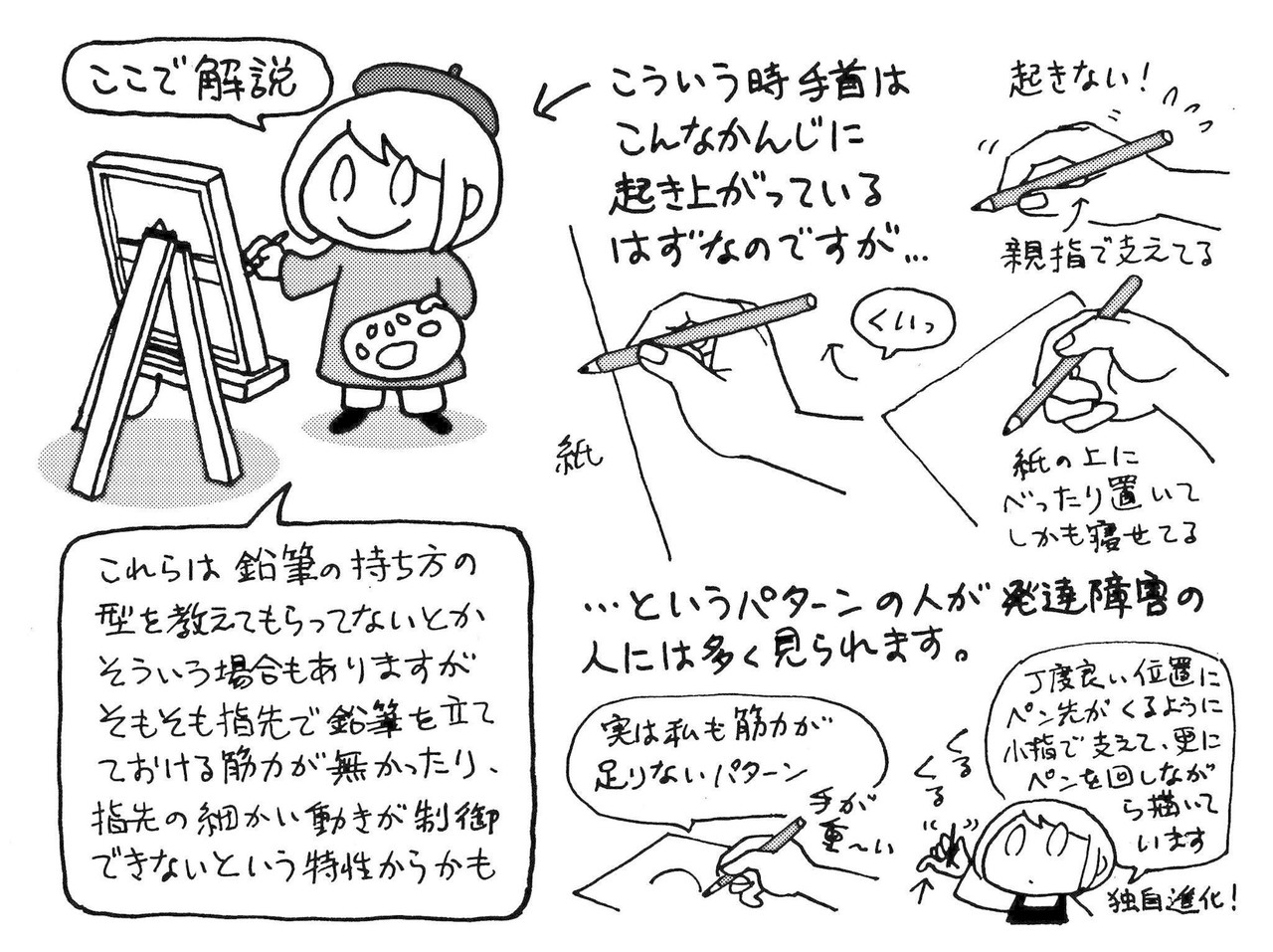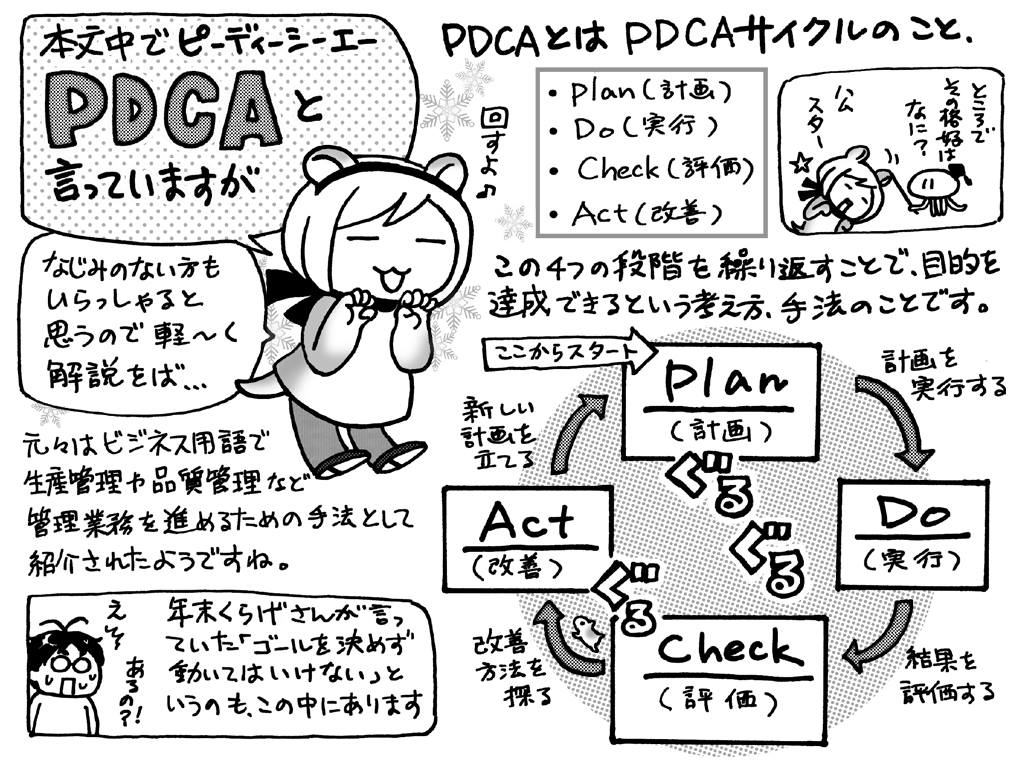こんばんは。くらげです。
noteを更新しました
今週の対談を更新しました。LDの人は多いのですがあまり問題にならないのはなぜというお話です。
災害に対する備え
先日、震災等から身を守るためにそろえている備蓄・避難グッズを紹介しましたが、今回は障害・病気に対する災害対策をメモ程度ですが書いておきます。
薬の持ち運びついて
震災で怖いのはいろいろと飲んでいる薬をなくすことです。あおの場合は抗鬱剤、自分の場合はADHDの薬がないと行動にかなり支障が出ます。
飲み忘れなどをかき集めて1週間分のストックを避難袋に入れており、日常的に飲んでいる薬もケースにまとめていて、さっと持って行けるようになっています。
あと病院と相談して頓服薬を少し多めに出してもらって、最悪これだけ飲んでおけば何とかなる、という組み合わせを確保しています。
お薬手帳について
お薬をある程度ストックしているとはいえ、交通や物流が大混乱におちいれば主治医のところに数週間はいけない、ということも想定できます。
そういう場合に備えて、お薬手帳のコピーを複数作って鞄に分散しています。震災時などはお薬手帳などを元に薬局が判断して処方することが可能になっているからです。
あおの場合はお薬手帳、頓服、コミュニケーションシート、自分の顔写真と名前、連絡先がわかる紙などのセットを作って、防水袋でくるんでいますね。自分はいつも持ち歩いている鞄にも障害者手帳や医療にかかる一式などを入れて持ち歩いています。
まぁ、特殊な薬も飲んでいるので、薬局にも十分なストックがあるとは思えないのですが、ないよりましかな、というところですが。
補聴器の予備・電池について
ボクはめがねと補聴器、人工内耳を使っています。というか、めがねと補聴器・人工内耳がなくなったら本当に何もできません。防災袋に古いめがねと古い補聴器、電池もケースに入れて突っ込んであります。
さすがに人工内耳の予備はないし、補聴器だけでは十分に会話はできないのですが音が聞こえるか聞こえないかでかなり判断力に違いが出る気がします。
避難所について
ボクもあおも地域包括支援センターにも災害時に安否確認・要支援者リストに登録しており、災害時に少しでもはやく福祉につながれるように工夫しています。
ただ、大震災が起きたとき、福祉的な仕組みは制度上はどうであれ、職員が出勤できない状態になって機能しないことが想定できます。なので、最初の3日間はなんとしても自力で生き延びることを前提にいろいろと対策していますが、3日~1週間後は少しずつ福祉的な機能も回復すると思うので、そのときに優先的に連絡が入ることはそれだけでかなり大きなメリットになりえます。
プライバシースペースの確保について
前回も書きましたが、避難所に避難しても、あおは慣れないところで人混みにさらされると容易にパニックになります。ですから、小型テントを購入し、他人から見えないスペースを少しでもできるようにしています。
また、避難袋には気持ちを落ち着けるおもちゃや耳栓・イヤーマフも入れており、避難所の外れの方にテントをたててイヤーマフをしておもちゃで遊んでいれば少しはましかな、とは。
顔について
あおは相貌失調症があり、ボクの顔を説明できません。なので、先ほども書きましたが自分の顔を印刷したものを持ち歩いていますし、万が一ぬれたり汚れたりしても大丈夫な古い自分の免許証も持っています。(免許証はがっしり作られていますので)
まぁ、気休めですけど
まぁ、震災はどこまで被害があるか、被害の規模などを想定し切ることはできませんので、「気休め」程度でしかないんですよねぇ。ここまでやっても無理なときは無理だし、そもそも第一波で死ぬときは死にますしね。それでも、というところですが。
踏ん張りましょう
まぁ、今回はこれくらいで。皆様、生き延びる準備をしつつ踏ん張りましょう。では。