こんばんわ。くらげです。
noteを更新しました。
今週の「くらげ×寺島ヒロ 発達障害あるある対談」を配信しました。
今回は寺島さんがオープンキャンパスで息子さんの支援について相談してきたことの見聞録です。
入学前の障害のある子どもの相談についてはあまりネットにも情報がないのでかなり役に立つと思います。有料ですが、興味あるならぜひお買い求めください。
DO-IT Japan一般公開シンポジウム後半
さて、本日は先日のDO-IT Japan一般公開シンポジウムの続きです。
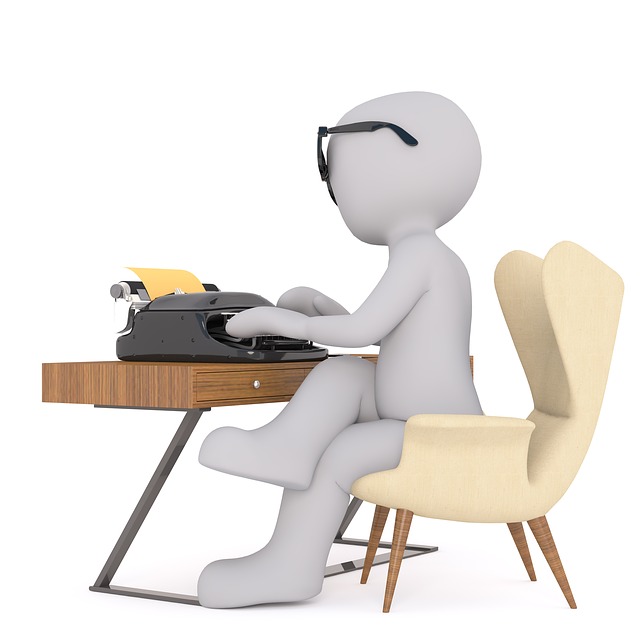
前半は話題提供でしたが、後半は各企業担当者を交えて、「企業における「新しい働き方」とは?「多様性」はどこまで許容されるのか」というテーマでのパネルディスカッションでした。
改革のモチベーション
まず、DO-IT Japanのコーディネーターより「各社の障害者雇用の改革についてのモチベーションはどこから来ているのか」という質問がありました。
ソフトバンクからは「障害児支援を行っていく中でICTで後押しすれば能力を発揮出来ることがわかったことが大きい」ということで、コーディネーターは「ICTによる環境支援の問題ですね」とコメントがありました。
富士通からは「合理的配慮の一般化」と法令が変わったことを挙げられました。具体的な支援に結びついたのは、人事課やカウンセラーそれぞれにノウハウがあったからとのこと。コーディネーターからは「ガイドラインを構築するメリット・デメリット」の話もありました。
マイクロソフトはもともとが外資でありライフスタイルを変えることを推進していてるとのこと。「外資の外圧」という言葉で端的にモチベーションを表現していました。
仕事の評価について
続いて、仕事の評価をどうすればいいのかという質問があり、各社とも「目標の設定」「評価軸の明確化」が大事だという話がありました。一方で給料の問題も話題に上がり、厚生労働省の方から障害者の就労に関する支援制度の説明がありました。
障害のある教員のコメント
つづいて、来場している東大の障害のある教授に二名に働くことについての意見を求める時間となりましたが、一人目は全盲の方で「障害があろうとなかろうが働かなくていいことが理想」との意見があり、続いて二人目の脳性麻痺の方からは「障害者が自分で障害について説明しなくてはいけないということに疑問がある。自分のニーズは何なのかはやってみないとわからないことが多い。」「働かなくてはいけないことからの自由が必要」というお話がありました。
子どもからの質問
子どもたちから質問もありましたが、その中でも「なんで障害者を専門的に支援する部署は各社にないのか」という疑問に対してある社からは「あまり支援をする必要がない障害者を雇用してきた。」という回答があったことがなかなかエキサイティングでした。
最後に各社からのまとめがあり、シンポジウム全体が終了しました。
シンポジウムを終えて:仕事から逃げられる社会へ
高度な4時間でした
さて、ざっくりと概要をまとめてみましたが、非常に高度で示唆的な内容に富む4時間となりました。
この場にいる子どもたちの将来のキャリアを考えるためにとても重要な機会となったことはまちがいないでしょう。
このへんの視点からは公式に資料が出来るでしょから特に触れないとして、ボク自身が感じたことを。
現状では「ユニーク」の範囲
各社ともユニークな就労支援を行っているのはわかったのですが、現状ではユニークな会社がユニークな取組をしている範疇だなぁと感じました。もちろん、こういう先駆的な取組を行ってるところが広まっていくのが大事なので、こういう働き方もある、ということが広まるがまず第一です。
一方で、こういう障害者の働き方改革は健常者の働き方改革と軌を一にするものだと特にマイクロソフトの話を聞きながら感じていて、そういう面では「特定の会社」の「障害者」に限定している限り社会的な障害者の働き方の改革は難しそうだと改めて思いました。
また、おそらくはポロリ、という感じなのでしょうが、「あまり支援する必要がない障害者を雇用している」というコメントは障害者雇用における障害の種類・重さの問題を端的に表現していましたね。
給与はどうなのよ
さらに、以前から障害者の給料の安さについて文句を言っているのですが、今回のシンポジウムでも給料について直接言及されることはなく、パネルディスカッションでちょっと「福祉の併用」を前提にしているような話がありまして、給与の安さに悩むものとしてはかなりモヤモヤしたものがありました。
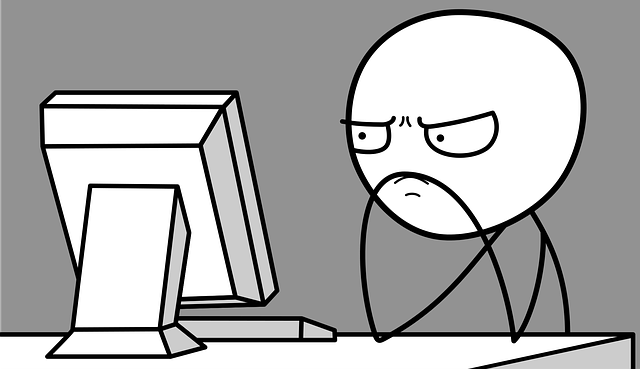
仕事をすることからの自由
むしろ、今回のシンポジウムで一番勇気づけられたのは、障害のある教授二人が「働くことから逃げる自由が必要」という意見があったことでした。ボク自身が障害を持って働くことを通して「なぜ障害があるのに働かなくてはいけないのか」という疑問を持つことは多いです。
正確に言えば「障害という重荷があって普通のことですらきついのに、さらに安い給料しかもらえない仕事しかないのに働く意味はあるのか?」という疑問です。
それに対しては「評価を正しくする」「ガイドラインを定める」という各社の方針は「働きやすくする」という意味では全く正しいのですが、先生方が話された「仕事をしなくていい自由」を求めるというパラダイムシフトこそが障害者も健常者も生きやすくなる方向性としてアリだなと。
もちろん、どうすればそういう社会が出来るかは現段階では不明というか、かなり問題があるのですが、それでも「働くことの意味」を変えていければ、という希望が持てました。まぁ、ボクが生きている間に達成できるかもわかりませんが。
踏ん張りましょう
というところで、今日はこれくらいで。皆さん、仕事をしなくていい社会になるように仕事しつつ踏ん張りましょう。でわ。


